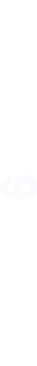用“订单”
支持中国机床产业!
支持中国机床产业!
点击开启


National Layout
全国布局
六地七展 驱动未来
2026金诺机床展总规模
520000
520000
平米
展出面积
6100
6100
家
参展商
640000
640000
人次
专业观众
Advantages
展会优势
01/03
大数据赋能会展新未来
Big data enables the exhibition to have a new future
-

4大
数据中心
300万+
采购商大数据
80%覆盖
装备制造业领域
100+行业
主流媒体矩阵运营
-

35万+
私域流量
100+
社群渠道独立运营
30+场
全年专项采购对接会
-

2000+家
品牌入驻云展
20000+台套
智能装备线上线下集中展示
80+场
直播会议
5000+场次
企业直播
开启数字会展新纪元,打造一站式机床工具中国采购平台!
01精准数字化营销
02供需商贸高效成交
03线上云展+传统会展”新模式,开启数字会展新纪元
Conference Forum
会议论坛
20国家
50场会议论坛
300位权威专家
3000位行业精英